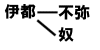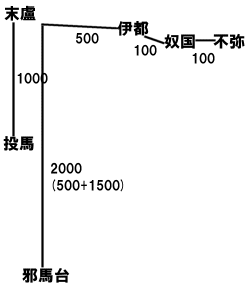|
P16
一世紀の倭と奴国
一世紀に入って、「倭奴国」(倭の奴国)が第一線上に登場する。後漢書に、
建武中元二年、倭ノ奴国、奉貢朝賀ス、使人自ラ大夫卜称ス。
倭国ノ極南界ナリ。光武、賜フニ 印綬ヲ以テス。
と記される国である。この奴国は魏志倭人伝のはじめの方に出てくる奴国であろうことは、志賀島から発見された金印「漢委奴国王」(委=倭)によっても証明される。儺県(なのあがた)、那津(なのつ)などの名で日本の史書にも記される、現在の博多付近にあった国である。ところが後漢書の撰者は、魂志・倭人伝の二十一旁国の最後に、
次有奴国、此女王境界所尽。
とある奴国と混同し、「倭国ノ極南界ナリ」と注記したのである。(注)
この奴国は、漢に倣って国家体制を整えていたらしいことは、「使人自ラ大夫卜称ス」の文章から想像できる。それに地の利を得ていたので、経済力も大きかったろうことが想像できる。一世紀において第一番目に名のりをあげたのも尤もと思う。
しかし漢王朝も倭地に通じていて、奴国王を倭国王とは認めなかった。倭(委の奴国という一部分を支配する王として認め、「漢委奴国王」の金印を授与したのも、これまた尤もなはなしであったと言えよう。
P17
このことは一面、建武中元ニ年(西暦五七年)ごろ、倭地に連合大国家が誕生していなかったあかしにもなる。単独の国が漢王朝に通じて、金印をもらったりした事実が、その何よりのあかしであろう。大国家の傘下に入れば、そういう勝手なふるまいができなくなることは、いうまでもない。魂志に「今、使訳通ズル所三十国」とあるのは、その反証になるように見えるが、そうではない。それは上に間接的にの文字を補って読む必要のある文である。邪馬台国時代に入って直接(監察者無しに)漢土に使者を送ることができたのは、邪馬台国しかなかったと思われる。その事は魂志のどこにも、傘下の小国が、使者を送ったりした事実が記されていないことからも知られる。
一世紀の後半、倭地には奴国のほかに、三つほどの国が勢力を伸長させつつあった。三世紀の呼び名で言えば、邪馬台、投馬、狗奴の諸国である。そして更に大連合国家への機運も着々と熟しつつあった。漢土や韓土の政情を見るにつけ、今や小国分離の時代ではないと思い知りつつあった。
(注) 三宅米吉氏説による。
二世紀の倭と邪馬台国の誕生
二世紀の初頭に、大連合国が誕生した。これが邪馬台国である。武力による統一であったか、平和的な話し合いによるものであったかはわからない。とにかく大連合国が生まれた。
P18
安帝永初元年、倭国王帥升等献生口百六十人、願請見再 (後漢書)
この安帝の永初元年は、西暦一〇七年に当る。この百六十人という巨大な数の生口を携えての請見は、その大連合国の出現を、漢王朝に告げるためのものであった。
「倭国帥升」のところは、引用書により、「倭面上国王帥升」「倭面土地王師升」「倭面土国王帥升」「倭両国」などに乱れていて、ヤマタイコク論者の物議をかもしているところであるが(注1)、引用文より原典の文を尊重して見てよいと思う。漢王朝から見て「倭国」と称し得る国がはじめて誕生し、「倭国王」と称し得べき人物が、はじめて出現したのである。その出現が唐突であるため、引用者はとまどい間違えて、いろいろに記しているのである。「倭国王帥升等」は「倭国王の帥(すゐまたはそち)升等(ら)」と読み、「升」は、邪馬台国の官名に出てくる「弥馬升」(注2)の升ではなかったかと思われる。つまり官名と固有名詞とを混同して記したものかも知れない。
景初二年(二三九)(注3)に、卑弥呼が現に献じた生口は「男生口四人、女生口六人」 の計十人であった。また後に壱(台)与が王となるに当って献上した生口は 「男女生口三十人」であった。それらに較べ、百六十人という生口は、桁外れのばかでかい数である。よほどの大変革がなければそのような桁外れな献上がなされるはずがない。
そして魂志や梁書をよく読めば、その大変革が何であったかを突きとめることができる。歴史家は、文章を部分的にしか見ないので「恐らく倭国王帥升も同じ倭国の奴国の王であったであろう」(榎一排氏『邪馬台国』43p)などと言っているが、とんでもない間違いである。(国王自身が漢地に赴いた如く見ているのもおかしい。)
P19
其ノ国、本亦男子ヲ以テ王卜為シ、住(とど)マルコト七・八十年。
倭国乱レ、相攻伐スルコト歴年、乃チ共ニ一女子ヲ立テテ王卜為ス。
(魂志・倭人伝)
と、
桓、霊ノ間、倭国大イニ乱レ、更々相攻伐シ、歴年主無シ。
一女子有り、名ヲ卑弥呼ト曰フ。年長ジテ嫁セズ、鬼神ノ道ニ事へ、
能ク妖ヲ以テ衆ヲ惑ハス。是ニ於テ、共ニ丈一丁テ王ト為ス。
(後漢書・倭伝)
と、
漢ノ霊帝光和中、倭国乱レ、相攻伐スルコト歴年、
乃チ共ニ一女子卑弥呼ヲ立テ王ト為ス。
(梁書・倭伝)
の三文がその問題を解く鍵となる。
後漢書の文は、後漢第十一代の桓帝(一四七−一六七)と第十二代の霊帝(一六八−一八八)の問に、倭の大乱があったことを言い、梁書の文は、霊帝の光和年中(一七八−一八三)に大乱があったのち、卑弥呼を王に立てたことを述べる。梁書の記述が何を典拠とするか不明だが、後漢書よりなお具体的になっていて、然るべき資料にもとずく文と見られる。従って卑弥呼が連合の盟主になったのは、一八三年頃と考えてよいだろう。
P20
右の後漢書と梁書の文だけ見ると、卑弥呼が初代の王の如き印象を受ける。だがその前に七、八十年、男王の時代があったことを語るのが魂志の文である。歴年主なき時を何年間と見るかが問題だが、一七八−一八三(光和年中)の五年間か、それ以下であることに間違いないだろう。仮にいま五年と見て、さらに男王時代の七、八十年を加えて、一八三年から差し引くと、紀元九八年−一〇八年という数字が得られる。これが新連合大国の誕した年代と想定される。
筆者は先に、一〇七年の生口百六十人の献上は、新連合国の誕生を漢王朝に報告するためのものであったと言ったが、右に得られた数字は大体においてそれに一致するのである。従って一〇七年より少し前に、紀元一〇〇年から一〇六年頃の間に新連合国「邪馬台国」が誕生したものと見てよいことになろう。これを年譜であらわせば、
紀元 事項
一〇〇
新連合国「邪馬台国」が生まれる。男王立つ。
一〇六
一〇七 漢王朝への使者の派遣。
一六八 倭国この頃から乱れはじめる。
一七八 歴年主なき戦乱時代に入る。
一八三 戦乱が治まって卑弥呼が女王になる。
P21
と略記できるであろう。これでわかるように卑弥呼は決して初代の女王ではない。その前に何人かの男王が居り、卑弥呼は何代目かの王になるものと山られる。当時の人は長命であったことが倭人伝に記されているが、七、八十年問もー人の王が治世したということは考えられない。必ずや何人かの王が交替しているものと見てよいだろう。魂志も後漢書も梁書も、卑弥呼を、卑弥呼だけを書き過ぎている。ために卑弥呼がはじめの王の如き印象を与えられるが、仔細に検討すれば、途中の人物であることが判明するのである。
(注1) 例えば井上光貞氏『日本国家の起源も「倭面土国」を採り、
「倭の面土国」とよむべきだと言っている。そのほかイト(伊都)と見たり、マツラ(末盧)と見たりする説もあるが、問題にならないと思う。
(注2) 第四章の邪馬台国の官名についての考察を参看。
(注3) 書紀所引の魂志及び梁書は三年とする。三年の誤りかも知れない。
大乱と倭人国襲撃事件
霊帝の光和年中(一七八−一八三)の大乱のきっかけになったのは、鮮卑の倭人国襲撃事件であったろうと考えることができる。歴史家も邪馬台国論者も、このあたりの事件については、全くと言ってよいほど無頓着だが、大事な事件と思われるので少しく詳細に述べてみたい。
冬、鮮卑、遼西ニ寇ス。光和元年冬、又酒泉二寇ス。縁辺責ヲ被ラズトイフコトナシ。種衆日ニ多ク、丑畜射猟食ヲ給スルニ足ラズ。檀石根乃チ自ラ徇行シテ烏集ノ秦水ノ広従数百里ニシテ、
P22
水停リテ流レズ、其ノ中二魚有ルヲ見テ、之ヲ得ルコト能ハズ。倭、網捕ニ善シト聞キテ、是ニ於テ東(方)倭人国ヲ撃チテ、千余家ヲ得ツ。徒シテ秦水ノ(水)上ニ置キ、魚ヲ捕へシム。以テ糧食ヲ助ク。光和中檀石槐死ス、時ニ年四十五。(後漢書・鮮卑列伝・第八十)が、その事件である。鮮卑が西に東に侵寇した姑果、種衆の数が殖え、食糧不足に陥った檀石槐が、それを補うのに秦水の魚を充てようとしたが、綱を打つ者がない。倭人が網打ちが上手だと問いて、東方の倭人国を撃って、千余家を獲得した。その倭人を秦水の水上に移して、魚を捕えさせ、糧食の助けとした、という文意である。(注)
この東方の倭人国は、恐らくは朝鮮の南端にあったものだろうと、私は考える。水に馴れず網を打つすべも知らない鮮卑が、船で対馬や壱岐を襲ったとは考えられないからである。騎馬民族は船にも強いという人もいるが、海を知らず、魚を捕える術も知らない人種が船に強いはずがない。必ずや陛つづきにあった倭人国を襲ったものであり、陸つづきなればこそ襲うことができたのだと考えてよいと思う。
ということは当時既に朝鮮南端に、小倭人国が存在したということでもある。「千余家」という数は、魂志・倭人伝の対馬国の「千余戸」不弥国の「千余戸」に匹敵する。全家が鮮卑に襲撃されたと見ても、小国家を形成するに足る家数であった。そしてこの時、この小国ほ壊滅したか、壊滅的打撃を受けたであろうが、それはともかくとして二世紀に既に朝鮮南端に倭人国が存在したらしいということは、三世紀以降の朝鮮を考える上に、極めて重要な事だと思う。
P23
一方この事件は、統一後間もない倭国の威信をたいへん傷つける事件でもあった。隷下の一国がむざむざと異民族により、襲撃掠取されてしまったのに、施す術がない。漢を頼ろうにも、その漢が手を焼いている鮮卑である。いっそ皆殺しにあったというのであれば、あきらめもつこうが、捕虜として連れ去られたとあっては、問題が尾を引く。この事件を一体どうしてくれるのかと、中央政府への日頃の不満が高まってゆき、遂に動乱に発展したものと思う。
そしてこの動乱の結果、男王による武力統治の時代が終って、新しく卑弥呼が女王になるのである。
(注) 魂志の鮮卑伝にも同趣の記事が「魂書日」の文中に賊っている。それにあっては「倭」「倭人国」が、「汗人」「汗国」になっている。それでも「汗人」や「汗国」は、他に聞かない名前で、全く採ることができない記述である。
以上駈足で述べて来たことをまとめると、次のようになろう。
一、紀元前十一世紀ごろ、周王朝に鬯草を献じたのは、沖縄、種子島あたりの倭人と推測され、日本最初の文明の灯は、先ず南島にともったであろう。
一、紀元前にそれが南九州に移り、日本最初の国家が生れたのも九州の南部であったろう。そしてそれが後の狗奴国になったものと考えられる。
一、一世紀に、博多あたりを中心とする奴国が勢力を得て、国々の主導的地位にのぼったと見られるが、この頃はまだ連合国家は生れていなかった。
P24
一、二世紀のはじめ垣、規模の大きい連合国家「邪馬台国」が誕生したと見られる。
一、二世絶後半には、朝鮮(南端)に倭人国がすでにできていたであろう。
一、二世紀後半仲倭国の大乱は、朝那の倭人国を、鮮卑が製撃をしたことに端を発するものであったろう。
一、大乱が治まって卑弥呼が女王になるが、卑跡呼は邪馬台国の初代の王ではなく、建国後七、八十年を経て立った途中の王である。
P25
第二章 魏志の倭人伝と邪馬台国の比定
魏志倭人伝
倭人ハ、帯方ノ東南、大海ノ中ニ在リ。山島ニ依リテ国邑ヲ為ス。旧(もと)百余国。漢ノ時朝見スル者有リ。今、使訳通ズル所三十田。郡ヨリ倭ニ至ルニハ、海岸ニ循ツテ水行シ、韓国ヲ歴テ、乍(あるい)ハ南シ乍(あるい)ハ東シ、其ノ北岸、狗邪韓国ニ到ル七千余里。始メテ一海ヲ度ル千余里。対馬国ニ至ル。
其ノ大官ハ卑狗卜日ヒ、副ハ卑奴母離卜日フ。居ル所絶島、方四百余里可(ばか)リ。土地山険、深林多ク、道路ハ禽鹿ノ径ノ如シ。千余戸有リ、良田無シ。海物ヲ食シテ自活シ、船に乗リテ南北に市糴ス。又南、一海ヲ渡ル千余里、名ヅケテ瀚海卜日フ。一大国二至ル。官ハ亦、卑狗卜日ヒ、副ハ卑奴母離卜日フ。方三百里可(ばか)り、竹本叢林多ク、三千許(ばか)リノ家有り。差々(やや)田地有リ、田ヲ耕セドモ猶食スルニ足ラズ。亦南北ニ市糴ス。又、一海ヲ渡ル千余里、末盧国二至ル、四千余戸有リ。山野ニ浜シテ居り。草木茂盛シテ、行クニ前人ヲ見ズ。好ク魚鰒ヲ捕へ、水深浅卜無ク、皆沈没シテ之ヲ取ル。
東南陸行五百里ニシテ、伊都国二至ル。官は尓支卜日ヒ、副ハ泄謨觚・柄渠觚卜日フ。千余戸有り。世々王有ルモ皆女王国ニ統属ス。郡使ノ往来ニ常ニ駐(とど)マル所ナリ。東南奴国二至ル百里。官ハ兄(ロは凹)馬觚卜日ヒ、副ハ卑奴母離ト日フ。二万余戸有リ。東行、不弥国二至ル百里。官ハ多模ト日ヒ、副ハ卑奴母離卜日フ。千余家有り。
南、投馬国二至ル、水行二十日。官ハ弥弥卜日ヒ、副ハ弥弥那利卜日フ。五万余戸可リ。南邪馬壱(台)国ニ至ル、女王ノ都スル所。水行十日、陸行一月。官ニ伊支馬有リ、次ハ弥馬升ト日ヒ、次ハ弥馬獲支卜日ヒ、次ハ奴佳革是(革+是)(て)ト日フ。七万余戸可リ。
カナ→かな(原本にはなし)
倭人は帯方の東南大海の中にあり、山島に依りて国邑をなす。旧百余国。漢の時朝見する者あり、今、使訳通ずる所三十国。
郡より倭に至るには、海岸に循って水行し、韓国をへて、あるいは、南しあるいは東し、その北岸狗邪韓国に至る七千余里。
始めて一海を渡ること千余里、対馬国に至る。
その大官は卑狗と日い、副は卑奴母離と日う。居る所絶島、方四百余里ばかり。土地は険しく深林多く、道路は禽鹿のみちの如し。千余戸有り。良田無く、海物を食して自活し、船に乗りて南北に市糴す。又南に一海を渡ること千余里、名づけて瀚海と日う。一大国に至る。官は亦卑狗と日い、副を卑奴母離と日う。方三百里ばかり。竹木そう林多く、三千ばかりの家有り。やや田地有り、田を耕せどなお食足らず、亦南北に市糴す。又一海を渡ること千余里、末盧国に至る。四千余戸有り。山海にそいて居る。草木茂盛して行くに前人を見ず。好んで魚鰒を捕え、水、深浅と無く、皆沈没して之を取る。
東南陸行五百里にして、伊都国に至る。官を尓支と日い、副を泄謨觚・柄渠觚と日う。千余戸有り。世々王有るも皆女王国に統属す。郡使の往来に常に駐(とど)まる所なり。東南奴国に至る百里。官は兄(ロは凹)馬觚と日い、副は卑奴母離と日う。二万余戸有り。東行、不弥国に至る百里。官は多模と日い、副は卑奴母離と日う。千余家有り。
南、投馬国に至る、水行二十日。官は弥弥と日い、副は弥弥那利と日う。五万余戸可リ。南邪馬壱(台)国に至る、女王の都する所。水行十日、陸行一月。官に伊支馬有り、次は弥馬升と日い、次は弥馬獲支と日い、次は奴佳革是(革+是)(て)と日う。七万余戸可り。
巻頭部分を掲出したが、邪馬台国関係の諸問題は此処に集約されている感がある。そのうち主要なものについては、後に取り出して考察することとし、今はその他の二、三の問題について注釈的説明を施しておきたいと思う。
○倭人ハ……在リ
前漢書の燕地の条に、
楽浪海中有倭人、分為二百余国。以二歳時来献見云。
とあり、魏略逸文の顔師古注の前漢書に、
倭在帯方東南大海中、依山島為国。
とある。「倭国」と書き出せば、統一された一国の感があり、そう見るには抵抗があるので「倭人」
で書き出したものであろう。
P27
○対馬国
対馬という文字が問題になる。これはツシマという音を現した文字ではないようである。「対」は、対(む)きあう二つの島(上島・下島)を指示し、「馬」は大を意味すると見られる。(韓国の学者、李夕潮氏の直話による。)属蜩(中国)、馬韓、馬川池(朝鮮)などの馬である。対馬島で「二大島」の意味になり、漢人もしくは韓人のあてた文字であろう。それを日本でもそのまま用い、ツシマと読んでいるが、慣例によるものである。
つしまのねは したぐもあらなふ かむのねに たなびくくもを
みつつしめのも
対馬能禰波 之多具毛安長南敷 可牟能禰尓 多奈婢久君毛乎 見都追思怒波毛 (巻十四、三五一六)
は、万葉集の東歌であるが、やはり「対馬」の文字を用いている。日本語のツシマは「津島」で、航海の途中に寄港する島の意だとする説がある。そして日本語で、「馬」を大の意に用いた明確な例を探しにくい。「其ノ地ニ牛・馬・虎・豹・鵲無シ」と、魏志に記されているのであるから、それも尤もなことだと言えよう。そのような事もあるが、対馬は三世紀の頃もツシマと呼ばれていたことは、間違いのないことと見てよいと思う。
○瀚海と一大国
「瀚海」になると、文字も読みも向うのものになる。倭人は、この海に名をつけなかったものであろう。よって倭の領海ながら、先方の名で記されることになったわけである。「名ヅケテ」の主語は、もちろん倭人ではない。それから「一大国」であるが、魏略逸文に「一支国」とあることから、大を支の誤字とされているが、必ずしもそうともいえない。ツシマを二大(島)の意で対馬(島)と書いた筆法からゆけば、イキを一大(島)と記すことはあり得ると見られる。一支も単にイキの音をうつすためならば「伊支」と記されたろう。伊都国、伊邪国など、イは伊の字を用いるのが通例だからである。従って後世の「壱岐」の壱にも、一つの意味が生き残っていると見るべきである。
○邪馬壱国
邪馬台国の誤りと見る説を採る。その理由については、諸家が述べ尽しているので、くわしくは立ち入らない。「壱与」も「台与」が正しいのかも知れない。また、
掖邪狗等壱拝率善中郎将印綬。
の「壱拝」も「台拝」かも知れない。(壱拝では意味が採りにくいが、台閣にて拝する意で台拝と言ったかも知れないことは考えられなくない。)
榎教授の伊都中心の放射線説批判
榎教授は、伊都国以前の諸国については、
方位・距離・地名
の順に記すのに対して、伊都国から後の国々は、
方位・地名・距離
P29
の順に記されている事に注意し、それまでの直線状に見る説を否定して、伊都国中心の放射線説を唱えられたことは有名である。私もはじめにこの説に接した時は、日を見張る思いがし、必ずやそうでなければなるまいと思ったものである。しかしその後いろいろ考えてみると、榎説にはかなりの無理があって従い難いと思うようになった。その無理と思われる点をこれから列挙して検討してみよう。
一、東を先に、南を次に記す方針と矛盾する点があること。
魏志倭人伝の撰者が、東を先に、南を次に記す方針で筆を進めていることは、
ヽヽ
倭人在帯方東南大海之中
ヽヽ
東南陸行五百里、到伊都国
ヽヽ
東南至奴国百里
などの例から知られる。これをひっくり返して南東と記すことはない。この精神からいけば、条件が同じ場合は、
東
東南
南
の順に筆を進めるはずである。
しかるに
東南陸行五百里、到伊都国……東南至事奴国百里…東行至不弥国百里
の奴国と不弥国の部分は、向じ百里ずつで条件が同じなのに、東南を先に、東をあとに記したことになる。榎氏は、
|